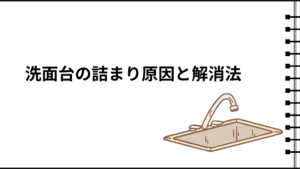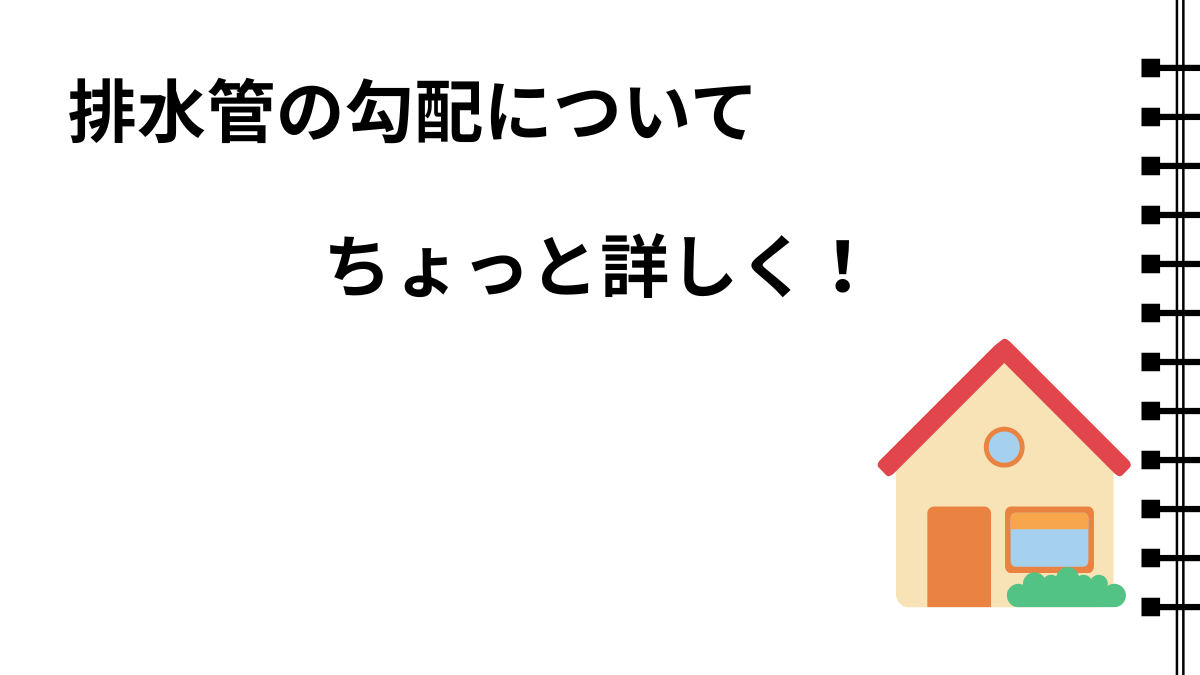トイレって実は詰まりやすいの、知ってました?
「いやいや、この前は洗面台も詰まりやすいって言ってたじゃん!じゃあ全部詰まりやすいんじゃないの?」
そんな声が聞こえてきそうですね。
でも、『最近のトイレ』は本当に詰まりやすくなっているんです。
今回は、その原因を深掘りしていきたいと思います。
今のトイレは「節水型トイレ」しかない
まずは核心から。
最近販売されているトイレは、ほぼ全てが「節水型」です。
昔のトイレと比べると、使う水の量は大幅に減っています。
経済的で環境にも優しい。とても良いことなんですが…その分、従来通りの使い方をすると「詰まりやすい」問題が出てきてしまうんです。
特に注意が必要なのが厚手のトイレットペーパー。
某有名ブランドの「ふわっとリッチな紙」なんかは、詰まりの原因としてよく名前が挙がります。
実際に高圧洗浄の業者さんと話をしても「最近はあのペーパーが詰まっているケースが多いんですよ」と教えてくれました。
さらに、流せるトイレクリーナーシートも要注意。
名前の通り流せる設計ではあるのですが、配管や勾配の環境によっては紙が溶けきらずに残ってしまい、詰まりのきっかけになってしまいます。
節水でエコに見えても、いざ詰まって修理を呼んだら数万円の出費。
これが最近のトイレ事情なんです。
節水なのにどうして詰まる?
「トイレは節水でも、ちゃんと流れるように設計されているんじゃないの?」
そう思いますよね。私も同じことを思いました。
実際、メーカーは設計段階で何度もテストを行い、節水でも十分流れるように作っています。
それなのに詰まりやすい現実がある…。
その原因の一つとして考えられるのが配管周りの状態です。
新築住宅で新しいトイレを設置した場合、配管も新品なので問題はほとんどありません。
ところが、古い住宅で「壊れたトイレを新しい節水型に交換した」ケースでは、詰まりが起こりやすくなるのです。
下水管の勾配と流れの関係
ここでポイントになるのが下水管の勾配(傾き)。
一般住宅の排水管は、通常「1%~2%」の勾配がついています。
1%とは、1メートル先で1センチ下がる程度のごくわずかな傾斜です。
「そんな緩やかで大丈夫なの?」と思うかもしれません。
でも、実はこれがベストなんです。
もし勾配が急すぎると、水だけが先に流れてしまい、固形物(紙や便)が取り残されやすくなります。
残ったものが配管に張りついてしまうと、そこから詰まりの原因になってしまうのです。
逆に1~2%程度の勾配なら、水と固形物がほぼ同じスピードで流れていくため、管内に残りにくくなります。
つまり節水トイレは、この正常な勾配が前提条件での設計になっていると言えるでしょう。
勾配が変わってしまう理由
では、なぜ詰まりやすくなってしまうのか。
答えは「勾配が変化してしまった」ことにあります。
新築当初は正常だった配管の勾配も、長年の間に地盤沈下などの影響で変わってしまうことがあります。
また、配管の継手(つなぎ目)部分に少しずつ汚れやカスが溜まり、それが障害物のようになって流れを妨げるケースもあります。
継手に汚れが原因の場合は、一度業者に高圧洗浄してもらえばスッキリ改善することも多いです。
ただし、勾配自体が変わってしまった場合は根本的な対策が必要。とはいえ工事となると費用も大きいので、まずは日常の使い方で工夫してみるのが現実的です。
簡単な対処法は「いつでも大で流す」
一番手軽で効果的な方法は、いつでも「大」で流すことです。
節水トイレは「小」と「大」で流れる水の量が違いますが、紙を使う以上「小」で流してしまうと水量が足りず、途中で詰まりやすくなってしまいます。
特に女性の場合はトイレットペーパーを使用する機会が多いので、「小」で流すのは正直おすすめできません。
紙が残ってしまい、それが積み重なるとやがて配管の中で障害物と化してしまうのです。
水の勢いは思った以上に大切で、ある程度の質量があるからこそ「押し流す力」になります。
日常のちょっとした工夫でトラブルを防げるなら、これは試して損はない方法ですね。
まとめ
最近のトイレが詰まりやすいのは、トイレ自体の設計が悪いからではありません。
節水型トイレは、あくまで正常な配管環境を前提に設計されているのです。
ところが、古い住宅で勾配が変わっていたり、長年の汚れが蓄積していたりすると、どうしても詰まりやすくなってしまいます。
今日からできる対処法
- 厚手のトイレットペーパーは控えめに
- 流せるシートも注意して使う
- 普段から「小」ではなく「大」で流す
たったこれだけで、詰まりのリスクはぐっと下がります。
節水でエコなのは素晴らしいことですが、結果的に高額な修理代を払う羽目になったら本末転倒です。
ぜひ一度、日頃のトイレの使い方を見直してみてください。