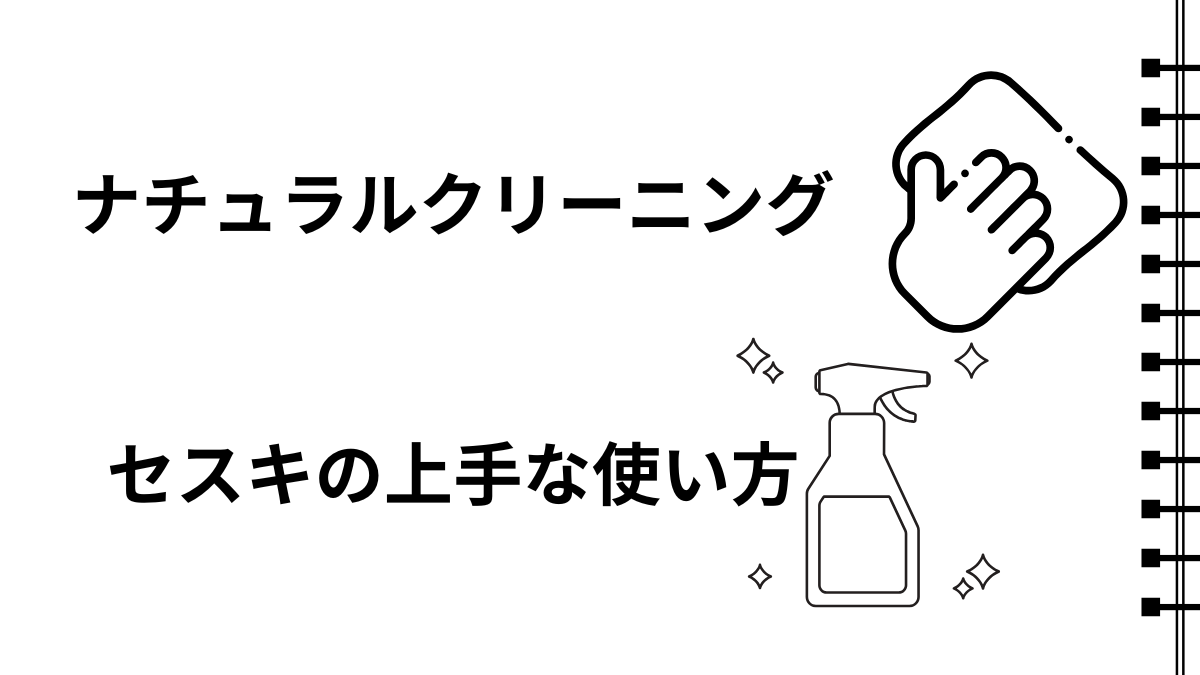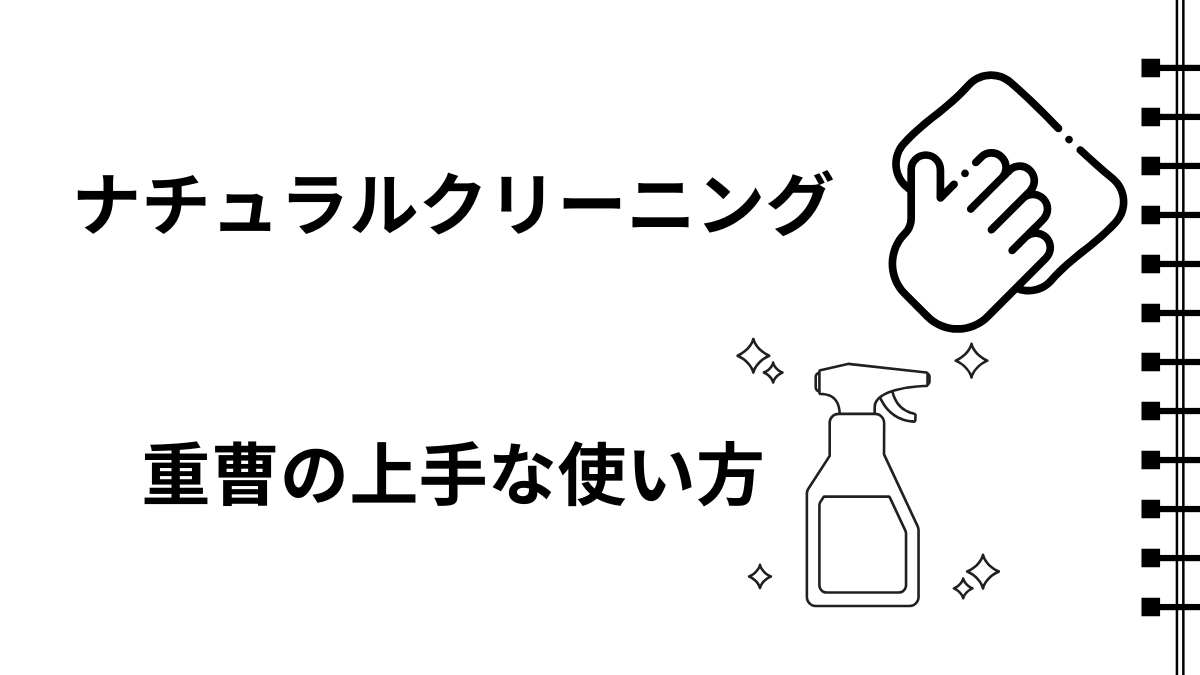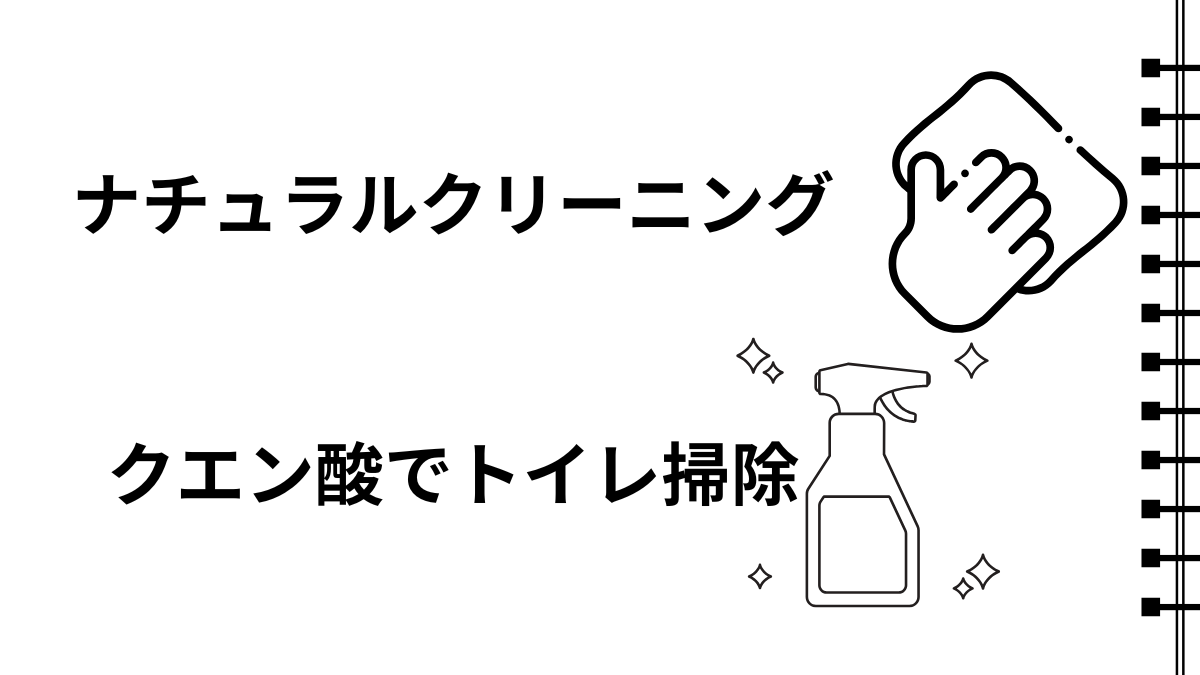セスキ炭酸ソーダ(セスキ炭酸ナトリウム)は、重曹に似た性質を持つ掃除の強い味方です。
人体や環境への負担が少なく、アルカリ性のため油汚れや皮脂汚れにとてもよく効きます。
見た目は白くて細かい結晶状で、水に溶けやすく、冬場でも扱いやすいのがうれしいポイントです。
今回は、キッチンや浴室、トイレなど、設備まわりでの具体的な使い方を紹介していきます。
セスキ炭酸ソーダの入手方法と目安量
セスキ炭酸ソーダは、スーパーやドラッグストアなどで簡単に手に入ります。
価格の目安は1kgあたり約500円前後(購入時期や店舗によって多少異なります)。
スプレー用の洗浄液を作るときは、水500mlに対してセスキ小さじ1(約10g)がちょうどよい濃さです。
この配合なら、1kgあれば500mlスプレーが約100本作れる計算。
とてもコスパが良く、家中の掃除に惜しみなく使えますね。
セスキ炭酸ソーダと重曹の違い
どちらも水に溶かすとアルカリ性になりますが、セスキ炭酸ソーダのほうがアルカリ度が強く、油汚れや皮脂汚れに対して洗浄力が高めです。
一方で、重曹には弱い研磨効果があるため、鍋の焦げ付きや茶渋などのこすり洗いには重曹の方が向いています。
つまり、「どちらが優れている」というよりは、得意分野が違うというイメージです。
しつこい油汚れにはセスキ、焦げやこびり付きには重曹、このように使い分けるのが賢いやり方です。
セスキ炭酸ソーダが得意な汚れ
セスキ炭酸ソーダは水に溶かすと弱アルカリ性を示し、酸性の汚れに強いのが特徴です。特に効果的なのは次のような汚れです。
- 皮脂汚れ(壁紙の手あか、ドアノブ周り、衣類の首元)
- 油汚れ(キッチンのレンジフード、コンロまわり)
- 血液や体液のシミ(衣類や下着など)
たとえば壁紙の手あかなら、スプレーして数分置いた後に乾いた布で拭くだけでスルッと取れます。
また、衣類の襟や袖口の皮脂汚れには、スプレーして軽くもみ洗いすると効果的です。
キッチンの頑固な油汚れは「つけ置き」で
スプレーしても落ちにくい頑固な油汚れには、「つけ置き洗い」がオススメです。
食器やコンロの細かい部品、レンジのフィルターなどには特に効果的です。
作り方と使い方:
- 洗面器やバケツにぬるま湯3Lを用意。
- セスキ炭酸ソーダを大さじ1入れてよく溶かします。
- 汚れた部品や食器を10分ほどつけ置き。
- その後、スポンジで軽くこすれば汚れが浮き上がって落ちやすくなります。
細かい隙間や、ベタつくけれど焦げついていない汚れなどに特に向いています。
また、スプレーで掃除する場合でも、汚れ部分にキッチンペーパーをかぶせて上からスプレーする「湿布法」もおすすめ。
汚れにじっくり浸透させることができます。
お風呂・トイレの掃除にも大活躍
セスキ炭酸ソーダには、軽い抗菌作用とカビ抑制効果があります。そのため、浴室やトイレの掃除にも利用できます。
使い方は簡単。セスキ水を吹きかけて、たわしやスポンジで軽くこするだけでOKです。
ただし、水垢や尿石のようなアルカリ性の汚れには効果が弱い点に注意が必要です。
これらは酸性洗剤(クエン酸やお酢など)を使うとスッキリ落とせます。
つまり、浴室の皮脂汚れにはセスキ、水垢にはクエン酸、この組み合わせがオススメです。
使用時の注意点
- 金属部分への長時間放置はNG。 一部の金属(アルミなど)は変色する恐れがあります。使用後は水でしっかりすすぎましょう。
- 肌への刺激に注意。 手荒れしやすい人はゴム手袋を使うと安心です。万一目や皮膚に入った場合はすぐに水で洗い流してください。
- 混ぜるのは厳禁。 酸性の洗剤(クエン酸・酢など)と混ぜると化学反応を起こす可能性があるため、絶対に併用しないようにしましょう。
ちょっとしたコツで効果アップ
- 汚れが強い場合は、濃度を少し上げる(例:水500mlにセスキ大さじ0.5)と洗浄力が増します。
- しつこい油汚れは、スプレー後にラップやキッチンペーパーで覆ってしばらく放置するのがコツ。洗剤が蒸発せず、汚れをしっかり分解してくれます。
- 焦げ付きや研磨が必要な汚れは、セスキより重曹を選びましょう。両方を使い分けることで、家中の汚れに対応できます。
まとめ
セスキ炭酸ソーダは、「ナチュラルクリーニングの万能選手」と呼ばれるほど、手軽で使い勝手のいい掃除アイテムです。
重曹やクエン酸と上手に組み合わせれば、洗剤をほとんど使わなくても家中ピカピカにできます。
環境にも優しく、手にもやさしいセスキ炭酸ソーダ。
日常の掃除に取り入れて、快適な住まいを保ってみてください。