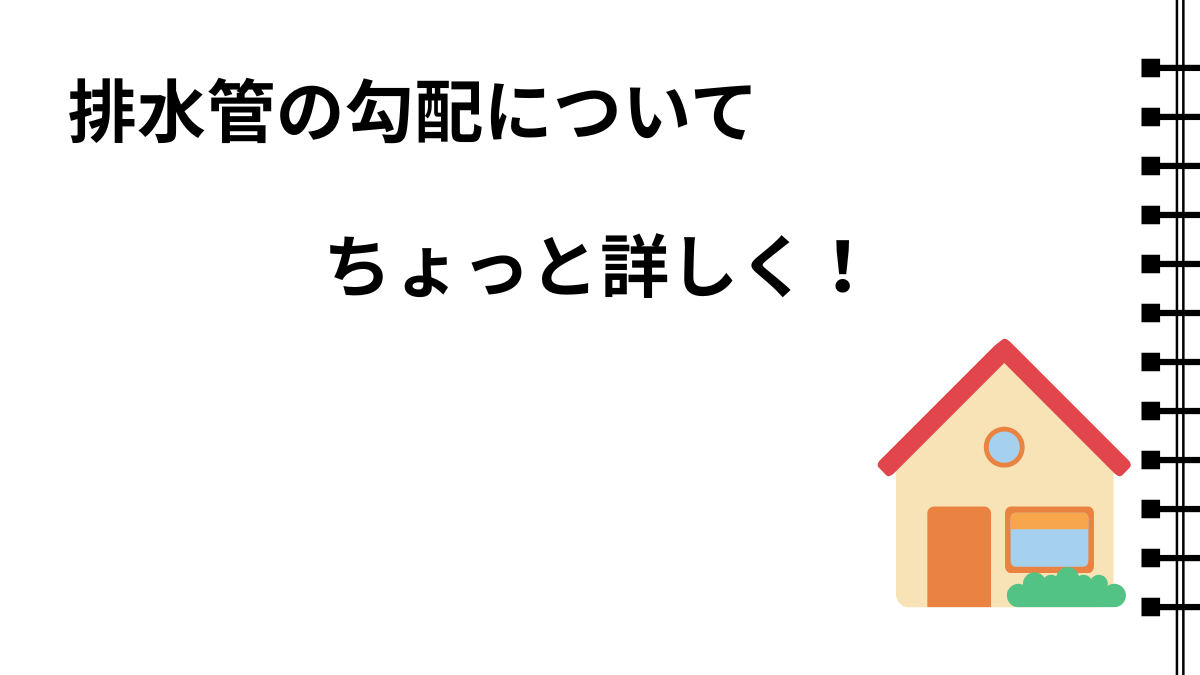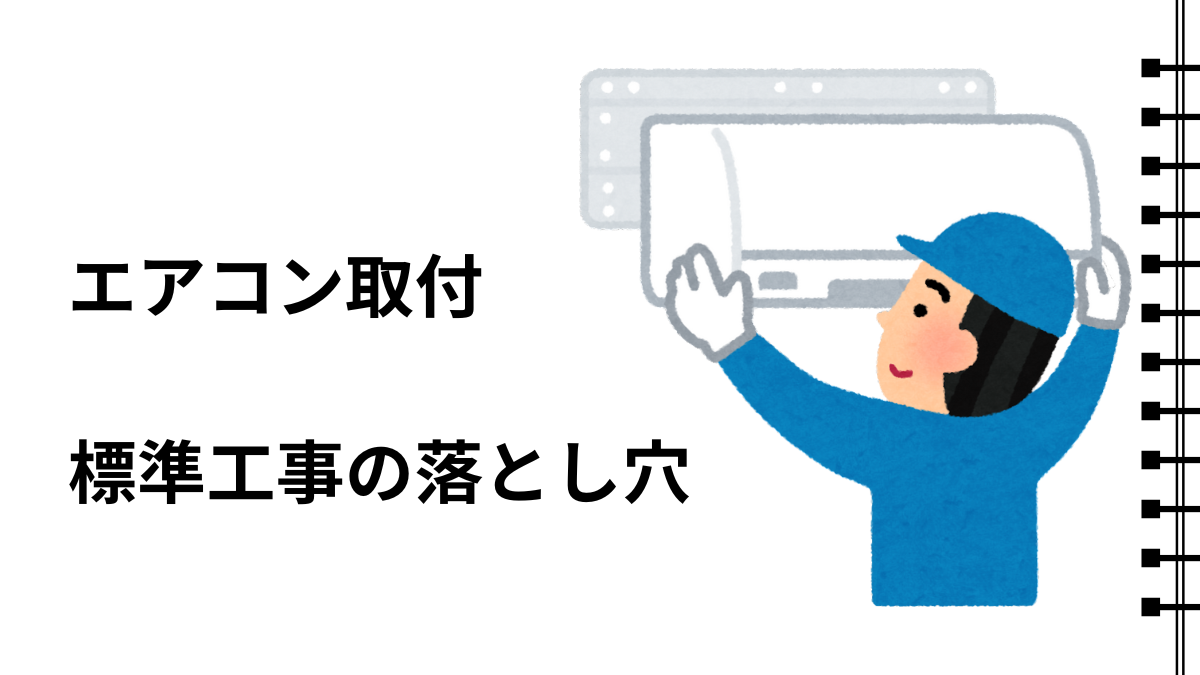下水管は見えないですし、普段の生活ではあまり意識することはないかもしれません。
私たちが使った水や生活排水をスムーズに流すために、下水管には勾配が付いています。
勾配とは簡単にいえば「傾き」のこと。
下水管には、ただ真っ直ぐに管を敷くだけではなく、水が自然に流れるように角度をつける必要があります。
もしこの勾配が適切でなければ、排水の流れが悪くなったり、詰まりやすくなったり、最悪の場合は逆流してしまうこともあるのです。
今回は、この「下水管の勾配」について深堀していきます。
なぜ下水管に勾配が必要なのか?
水は高いところから低いところへ流れます。
高いところにから低いところに水がさかのぼって流れるなんてことはありません。
しかし、単純に「急な角度をつければよく流れるだろう」と思うのは間違いです。
勾配がきつすぎても、逆に緩すぎてもトラブルの原因になります。
- 勾配が急すぎる場合
水だけが先に流れてしまい、固形物や汚れが管内に残ってしまいます。
残った汚れはやがて固まり、詰まりの原因となります。 - 勾配が緩すぎる場合
水の流れが遅くなり、排水が管内に残ってしまいます。
これも汚れの付着や臭いの原因につながります。
つまり、下水管の勾配は「ちょうどよい角度」が必要なのです。
下水管勾配の基準
下水管の勾配には、建築基準法や下水道法などに基づいた指針があります。
一般的には「1/50~1/100」の勾配が必要とされています。
- 1/50(2%)の勾配 → 1m進むごとに2cm下がる
- 1/100(1%)の勾配 → 1m進むごとに1cm下がる
この範囲が、排水がスムーズに流れる傾きなのです。
ただし、管の太さによっても適切な勾配は変わります。
- 小口径(φ75~100mm程度):1/50以上
- 大口径(φ150mm以上):1/100程度でもOK
実際の現場では、設計図面や施工基準に従って勾配が決められています。
ちなみに一般住宅の設備のほとんどは、50mm~75mmが使われています。
100mmの下水管が使われているのは、トイレとメイン管(最終的に合流する管)くらいです。
勾配の測り方・確認方法
勾配は施工時にきちんと設定されていても、長年の使用で沈下や歪みが起きることがあります。
特に戸建て住宅では、地盤沈下や地震などで下水管の傾きが狂うことも。
勾配を確認する方法としては以下のようなものがあります。
- 実際に水を流して確認
水の流れがスムーズか、滞留がないかを見ます。 - ファイバースコープ調査
リフォームや修理の際には、管内カメラで実際の状態を確認することもあります。
カメラで確認することで桝以外の場所で水が溜まってないかなど調査します。
建物を建築の際、水道局立会いの下、水の流れは問題ないか、排水管の深さは設計図通りに施工されているかなど確認があります。
なので、最初から勾配が狂っていることは基本的にありません。
勾配不良が引き起こすトラブル
勾配が正しく取れていないと、日常生活にさまざまな影響が出ます。
- 水の流れが悪い
- 排水口からゴボゴボ音がする
- 頻繁に詰まる
これらの症状は「勾配が足りない」「逆勾配になっている」などのサインかもしれません。
逆勾配とは、本来下がるべき管が途中で上向きになってしまい、水が溜まる状態のこと。
この場合は部分的な掘削や入れ替え工事が必要になることもあります。
勾配を意識したメンテナンスの重要性
勾配は見えない部分なので、普段の生活では気づきにくいのが難点です。
しかし、日常的な点検やメンテナンスでトラブルを防ぐことができます。
- 定期的に大量の水を流す(浴槽や台所の水を一気に流すなど)
- 排水口のゴミ受けを掃除して固形物を流さない
- 異常を感じたら早めに専門業者に相談する
特に古い住宅では、勾配のズレが原因で排水不良を起こすケースが多いため注意が必要です。
まとめ
下水管の勾配は、排水の「流れやすさ」を左右する非常に大切な要素です。
- 勾配が急すぎても緩すぎてもNG
- 一般的な基準は1/50~1/100
- 勾配不良は詰まりや悪臭、逆流の原因に
- 定期的な点検やメンテナンスでトラブル防止
普段は目に見えない部分なので気が付きにくいですが、もし「最近排水の詰まりが気になる」と感じたら、一度プロに相談してみるのも良いでしょう。