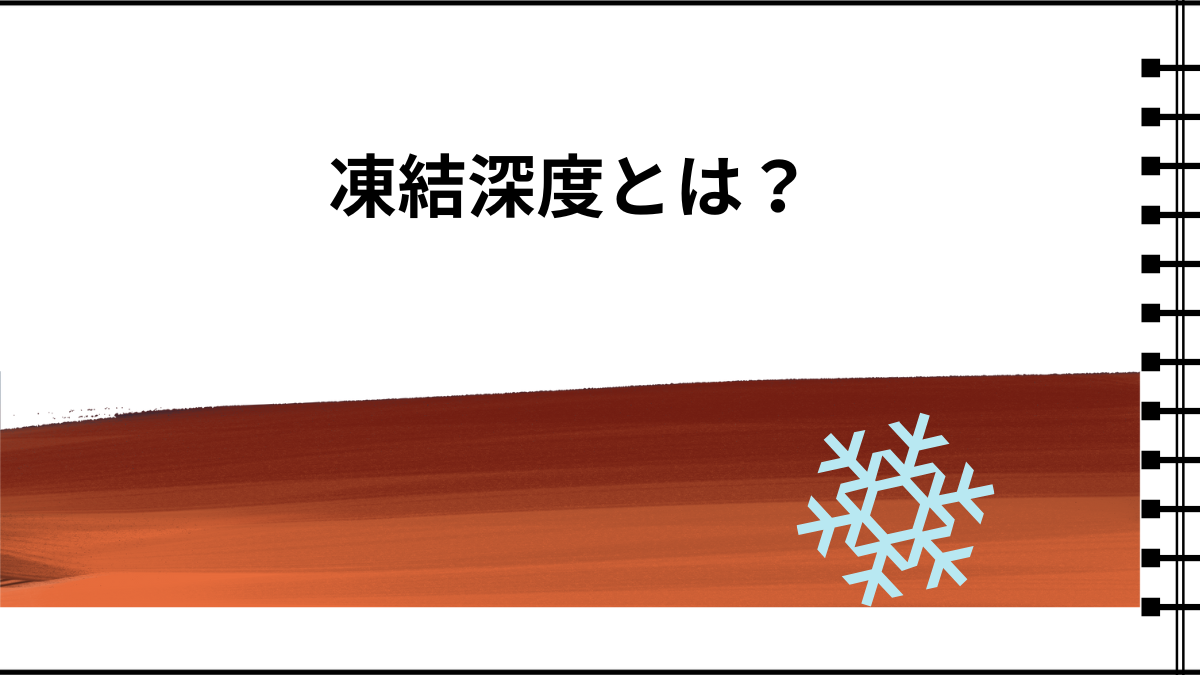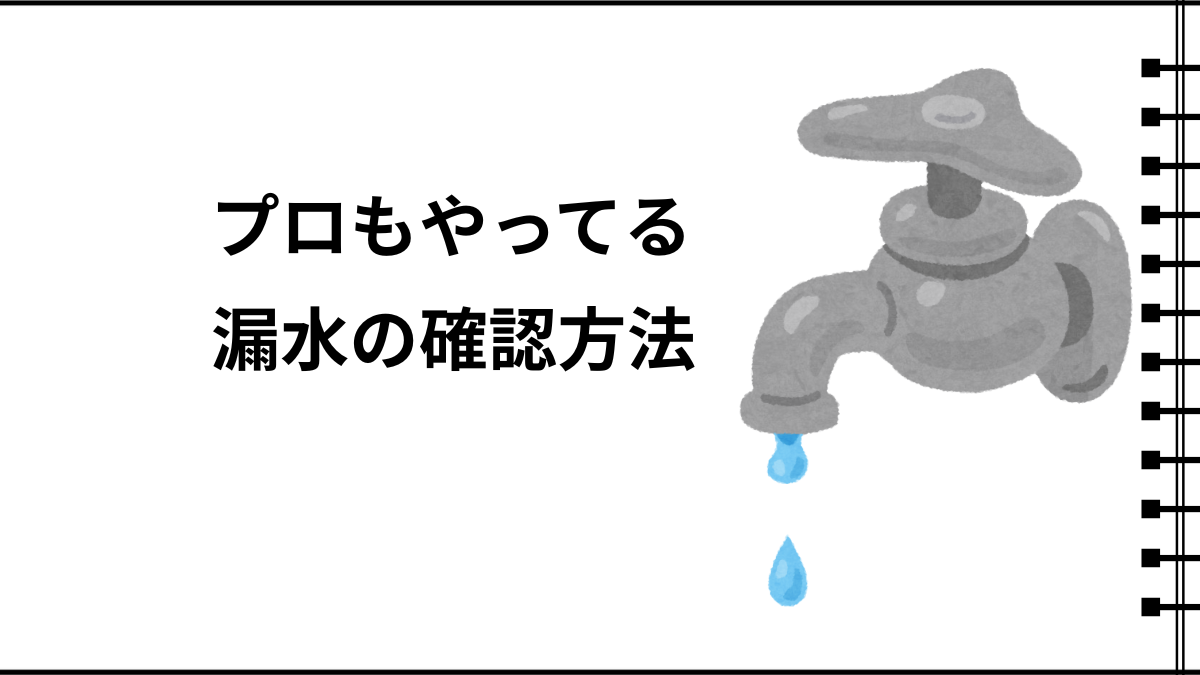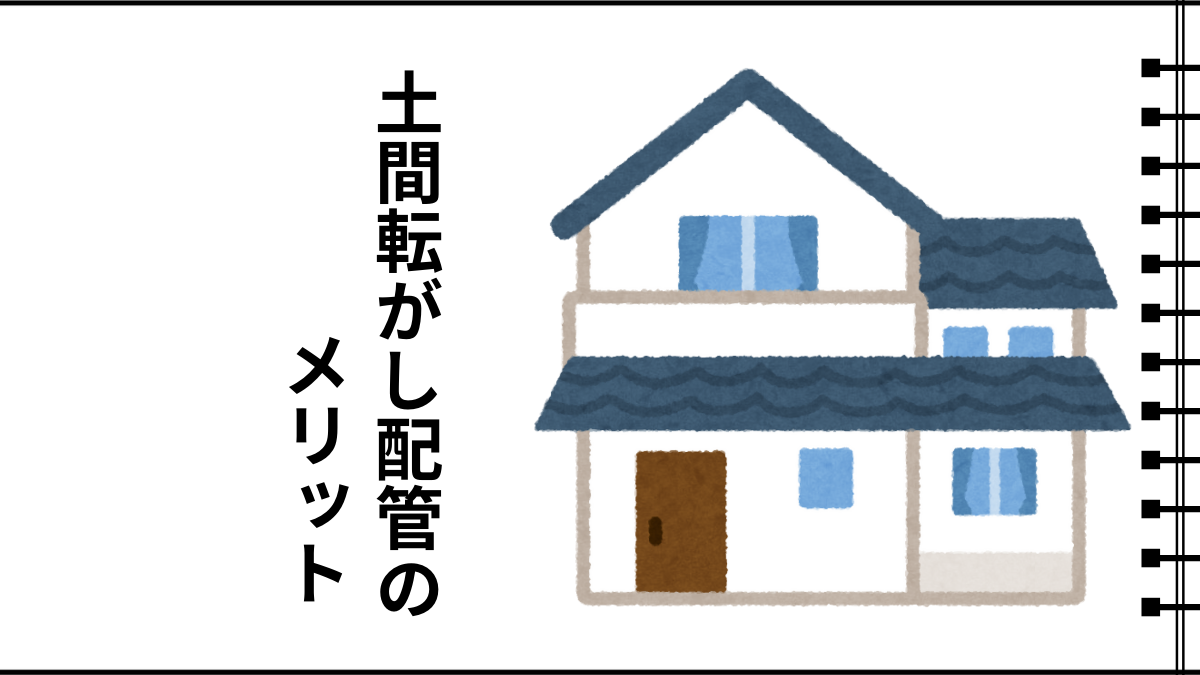「凍結深度」って聞いたことありますか?
日常生活ではまず耳にしないワードですが、水回りの工事や住宅設備に関わる仕事をしている人にとっては、とても大事なキーワードなんです。
今日はこの「凍結深度」について、できるだけわかりやすく書いていきます。
凍結深度とは?
凍結深度は「不凍深度」と呼ばれることもある言葉です。
漢字を見ればイメージできるかもしれませんが、これは「地面が凍らない深さ」のことです。
冬になると、地表付近は冷え込んで土の中まで凍ってしまいます。
ですが、地中は深くなればなるほど外気の影響を受けにくく、ある一定の深さを超えると凍らなくなるんです。
つまり凍結深度とは、「ここまで深くなれば凍らない」とされる基準の深さのことなんですね。
設備屋さんにとってなぜ重要なのか?
じゃあ、なぜこの凍結深度が設備屋さんにとって重要なのか?
答えはシンプル。水道管を通すときに必ず考慮する必要があるからです。
地面の浅いところに水道管を埋めてしまうと、冬の冷え込みで簡単に凍ってしまいます。
そうなると水が出なくなったり、水道管が破裂してしまう危険性もあります。
エコキュートも普及してきましたが、夜に凍結して水がないと朝起きたらお湯ができてない!
なんてトラブルが発生してしまいます。
逆に、凍結深度よりも深く埋めておけば、基本的には凍る心配はありません。
だからこそ、施工時には必ず「この地域の凍結深度」を守ることが求められているんです。
実は地域によって違う!水道管の深さ
私も仕事で初めて知ったのですが、水道管の埋設深さって地域によって全然違うんですよ。
例えば、比較的暖かい地域では30cm程度の深さでも大丈夫ですが、寒冷地では1m以上、場合によっては150cmくらい深く埋めないといけないこともあります。
これは各自治体ごとに「最低何センチ以上」とルールが定められているんです。
北海道と九州で同じように水道管を埋めてしまったら大変ですよね。
寒い地域では当然、より深く埋めなければならないわけです。
こうした地域ごとの基準を守らないと、「ちょっと冷え込んだだけで凍結してしまい、水が出なくなった…」なんて事故につながってしまいます。
もちろん、想定以上の大寒波が来ればそれでも凍結のリスクはゼロではありません。
ですが、自治体が定めた深さを守って施工していれば、通常の冬であれば凍る心配はほとんどありません。
凍結深度が深いと起こる問題
ここでこんな疑問を持つ人もいるかもしれません。
「だったら、どの地域でも思い切って深く埋めればいいんじゃない?」
たしかに、深く埋めれば埋めるほど凍結のリスクは下がります。ですが、実際にはそう簡単ではありません。
なぜかというと、工事費用が高くなるからです。
工事費用が高くなる理由
水道管を深く埋設するためには、その分だけ地面を掘り下げる必要があります。
当然、掘削の手間が増えれば工賃は高くなりますよね。しかもそれだけではありません。
- 掘り出した土(残土)の処分費用がかかる
- 水抜き栓を長いものにしなければならないため、部材費が上がる
- 配管作業自体の手間も増える
といったように、工事全体のコストが膨らんでしまうんです。
だからこそ、施工業者は「その地域で必要とされるぎりぎりの深さ」で見積もりを出すのが一般的なんですね。
まとめ
凍結深度とは、「地面が凍らない深さ」のこと。
この深さを守って水道管を埋設しないと、冬場に凍結して水が出なくなったり、水道管が破裂したりするリスクがあります。
- 地域ごとに基準が違う(30cm~150cm程度)
- 深く埋めれば安心だが、その分工事費用は高くなる
- 自治体の基準を守っていれば、通常の冬では凍結の心配はほとんどない
普段は気にすることのない言葉ですが、実は私たちの生活を守るうえでとても大切な存在なんですね。
冬になると「水道管の凍結」というトラブルがニュースで取り上げられることがあります。
そんなときに「凍結深度」という言葉を思い出してもらえたら嬉しいです。