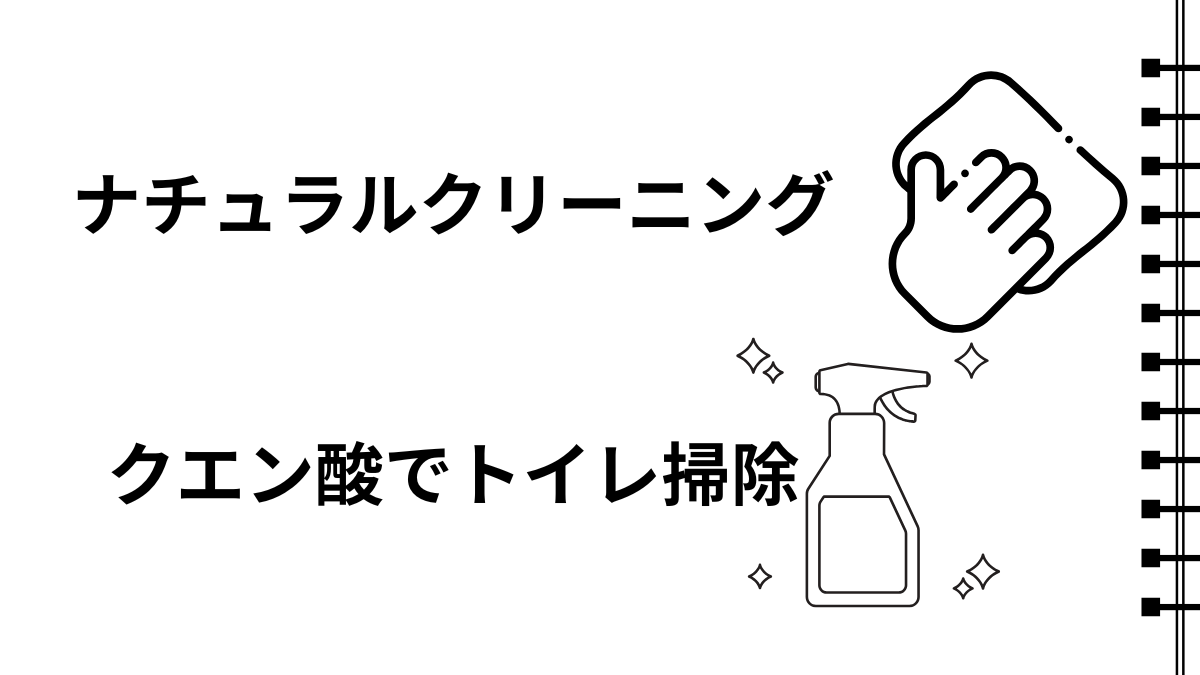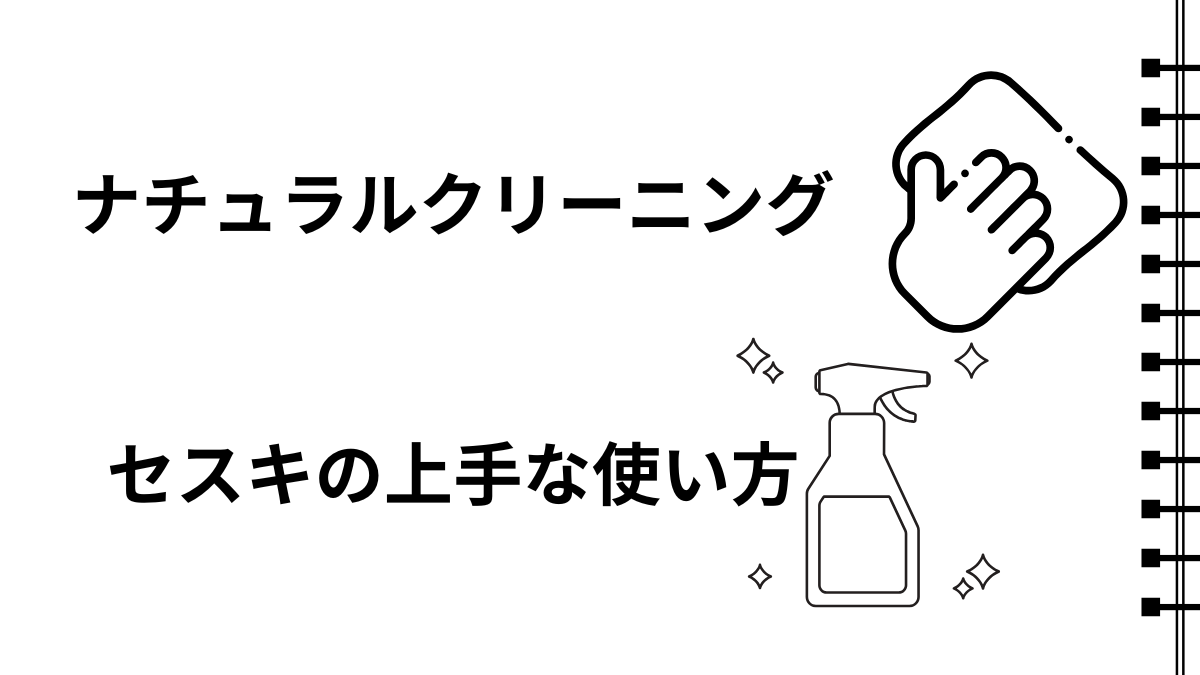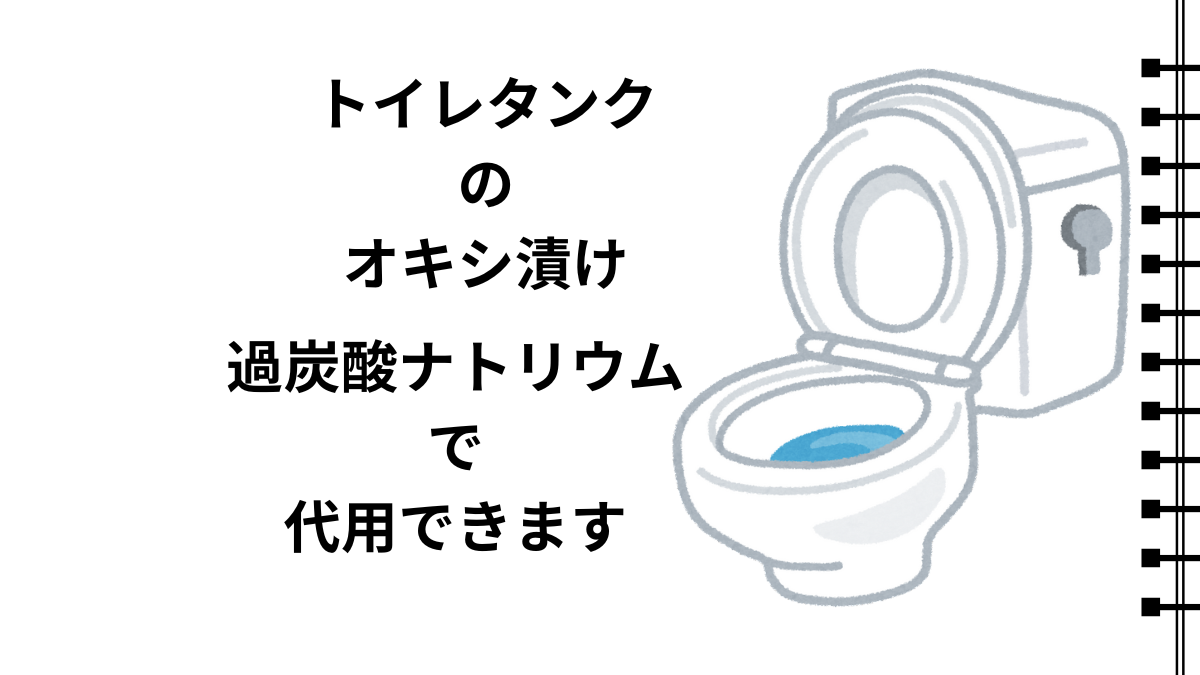ナチュラルクリーニングでよく使う重曹やセスキは弱アルカリ性。
酸性の汚れには強いのですが、逆にアルカリ性の汚れには弱いという特徴があります。
トイレに多い汚れはアルカリ性のものが多く、代表格が「尿石(にょうせき)」です。
そこで頼りになるのがクエン酸。今回はクエン酸にスポットを当てて、落とし方と予防法をわかりやすくまとめます。
尿石はなぜ厄介なの?
尿石は時間が経つほど固くなり、普通の掃除では落ちにくくなります。
無理に力任せでこすると便器表面に傷がつき、その傷に菌が入り込むと汚れが余計に落ちにくくなることも。
焦らず正しい方法で少しずつ落とすことが大切です。
準備するもの(まずはこれだけ)
- 水 200ml
- クエン酸 小さじ1/2(※濃度およそ1%)
- スプレータイプのボトル
尿石はアルカリ性なので、酸性のクエン酸水が有効です。
まずは使いやすいクエン酸水を作りましょう。
クエン酸パックのやり方(簡単&安全)
- 水200mlにクエン酸小さじ1/2を溶かしてクエン酸水を作る。
- クエン酸水をスプレーボトルに入れ、尿石や黄ばみ部分にたっぷり吹きかける。
- 上からトイレットペーパーを貼り、さらにクエン酸水を追加で吹きかける(パック状態にする)。
- 約10分置いた後、トイレの水を流してからブラシで軽くこする。
手軽で刺激も少ないため、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。
ただし、クエン酸だけで完全に取れないこともあるので、その場合は次の方法を試します。
頑固な尿石には「削り取り」も検討
クエン酸でも落ちない頑固な尿石には、メラミンスポンジや耐水性の細かいサンドペーパーでやさしく削る方法があります。
【用意するもの】
- メラミンスポンジ または きめの細かいサンドペーパー
- クエン酸水
手順:尿石の表面をクエン酸水で湿らせ、スポンジや紙やすりを軽く濡らしてから、優しくこするように削ります。
注意点:この方法は陶器製の便器本体のみに使用してください。プラスチック製の便座や蓋には使うと傷むので絶対に避けましょう。削るのが不安な場合は、無理せずハウスクリーニングなどのプロに依頼するのがおすすめです。
トイレタンクには使わないで!
クエン酸水は安全ですが、トイレタンク内には使わないでください。
タンク内にはゴムパッキンや樹脂、発泡スチロールなどがあり、酸によって劣化する恐れがあります。
余ったクエン酸水は浴室の水垢掃除などに使うのが無難ですが、天然大理石や一部金属など酸に弱い素材には使わないでください。
尿石を予防するコツ
予防①:水をしっかり流す
排泄後に尿をしっかり流すことが最も基本。
節水型トイレなどで水量が少ないと汚れが残りやすいので、気になるときは追加で流す習慣をつけましょう。
予防②:クエン酸スプレーをこまめに活用
トイレ使用後に便座裏や便器内に軽く吹きかけておくだけで、尿石のもとになる尿素を抑えられます。
クエン酸水は作り置きで2〜3週間が目安。便利に使うなら小さなボトルで常備しておくと楽です。
壁紙や床の黄ばみもクエン酸で落とせますが、拭き取りはトイレ専用の使い捨てクロスを使うと衛生的です。
掃除のちょっとしたコツ
- 100円ショップのブラシを活用:直線タイプは力を入れやすく底や側面に、曲線タイプは便座裏やふち裏に適しています。スポンジブラシは細かいすき間に便利。用途に合わせて使い分けましょう。
- 水を一度抜いて磨く:便器底の水が邪魔な場合、紙コップですくって一度抜くと直接磨けて効果的。掃除後に戻して流せばOKです。
まとめ
尿石は放っておくと厄介ですが、クエン酸パック→(必要なら)やさしい削り取り→日常のクエン酸スプレーで予防という流れで十分に対応できます。
無理に力を入れて傷を付けないこと、タンクやプラスチック部分には使わないことを守れば、安全にきれいを保てます。
気になる汚れは早めに対処して、清潔なトイレを維持しましょう。